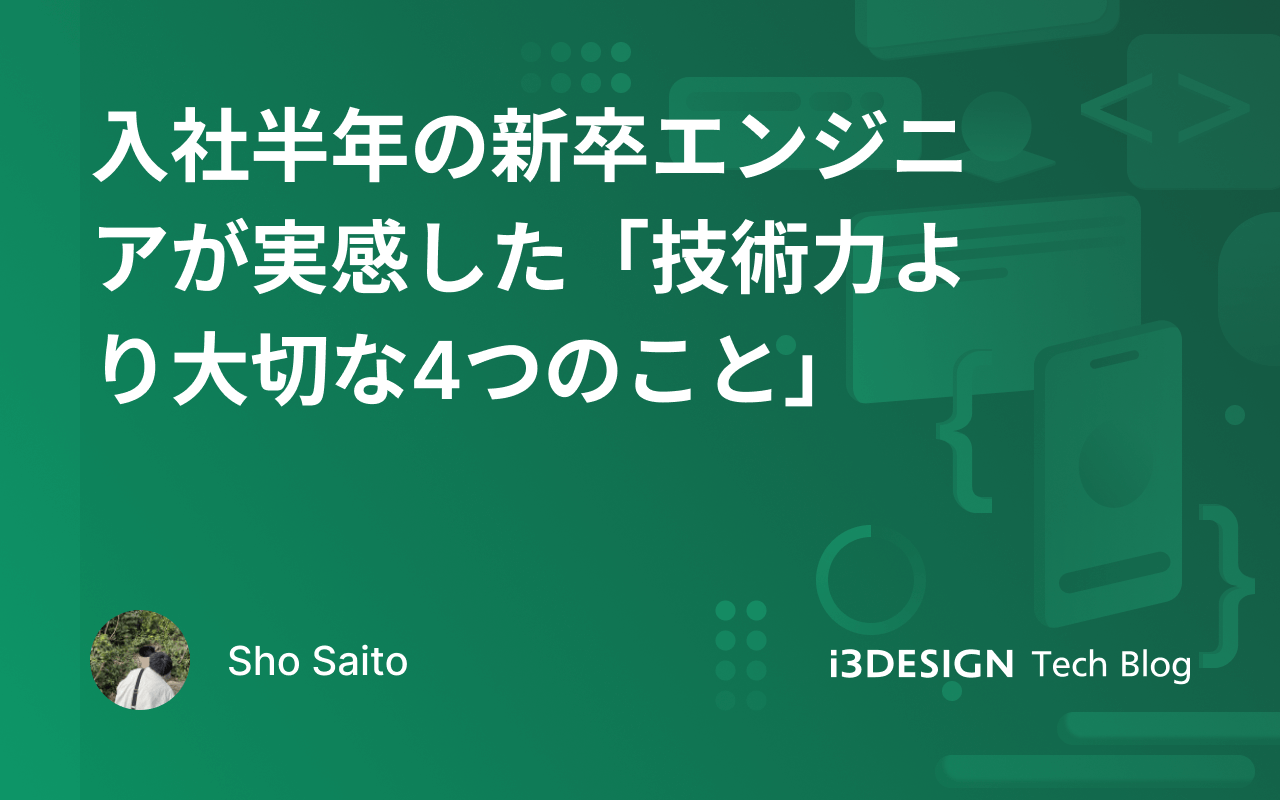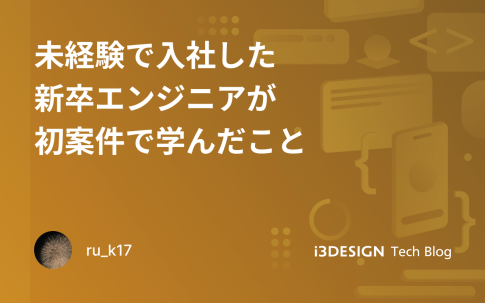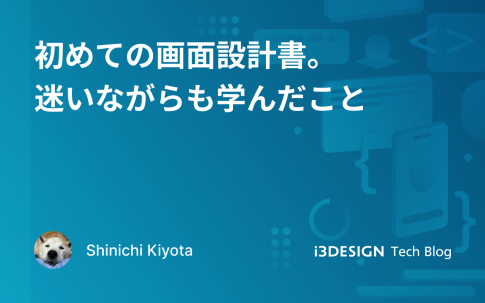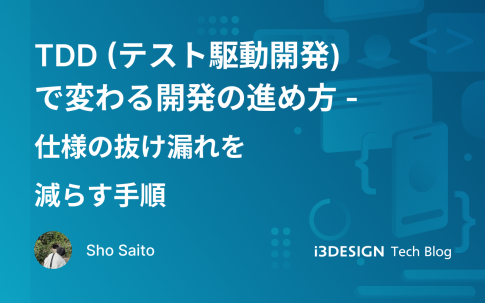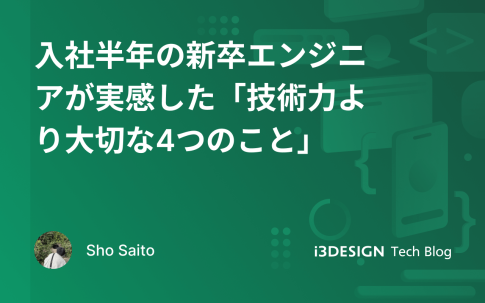はじめに
こんにちは。エンジニアの齊藤です。
こちらの記事で紹介のあったNittaくんと同じく、私は2025年4月に新卒として入社しました。
> 新卒1年目、初めてのプロジェクトで得た学びと気付き
入社後はビジネス研修やマナー研修を経て、フロントエンドの研修に進みました。
フロントエンド研修では、最初にコーディング試験を行い、その結果から個々の課題を洗い出して、苦手分野を重点的に学習できる内容でした。
入社前のプログラミング経験は、大学の授業や無料のプログラミングスクールでの学習が中心で、弊社で主に扱うReactやTypeScriptには全く触れたことがありませんでした。
研修時のコーディング試験では、オブジェクト配列の扱いにも苦戦したことをよく覚えています。
研修期間中は、一つ上の先輩にサポートいただきながら、諦めずに課題を一つずつ乗り越えていきました。
そして入社から1ヶ月後、初めてのプロジェクトにアサインされました。
そのプロジェクトには、研修のときにお世話になった先輩も参加しており、安心して現場に入ることができました。
初めてのプロジェクトはモバイルアプリの開発案件で、設計フェーズから参画しました。
画面項目定義書の作成や、レビューを受けながらの設計業務、フロントエンドの実装まで行いました。
この半年間のプロジェクト経験で、私は 「技術力以上に大切だと感じた4つのポイント」 に気づきました。
- 自分の技術不足を補うAIとの向き合い方
- タスクを自分が理解できる粒度に分解する力
- わからないことをわからないと言う勇気
- 自分の進捗や疑問を正しく伝えるコミュニケーション
本記事では、これら4つの観点から、新卒エンジニアとして現場で学んだリアルな気づきをお話ししたいと思います。

自分の技術不足を補うAIとの向き合い方
AIツールは、今の開発現場では欠かせない存在になっていると感じます。
私自身も日々のコーディングでAIを活用しており、実装のヒントを得たり、エラーの原因を早く見つけたりと、大きな助けになっています。
一方で、AIの提案を「理解しないまま」使ってしまうと、思わぬ課題が生まれることもあると感じました。
たとえば、複雑なロジックが絡む際にAIが生成したコードをそのまま使った結果、自分でも「なぜこう動くのか」を説明できないまま進めてしまったことがありました。
その状態でチームメンバーからレビューの際に、
「この実装、どういうロジックで動いているの?」
と聞かれたとき、うまく説明することができず、結局レビューしていただく先輩が1からコードを読み解くことになってしまい、余計に時間がかかってしまったことがありました。
そうした経験から、大袈裟かもしれませんが、自分が実装した箇所については、自分がいちばんの理解者であり、責任を持つべきなのだと強く感じました。
目の前のタスクを終わらせることに必死になって、AIの回答をそのまま受け入れてしまうのではなく、「なぜそうなるのか」「他にどんな書き方があるのか」を自分なりに考えて理解することが大切だと感じました。
AIはとても頼もしいツールですが、自分で考える時間を削り、結果としてチームメンバーに迷惑をかけてしまう危うさもあると感じています。
うまく活用しながらも、最終的には自分の理解として落とし込む姿勢を大事にしていきたいです。
タスクを自分が理解できる粒度に分解する力
私がプロジェクトに参加した当初は、タスクの全体像をつかめないまま「実装していけばそのうち理解できるだろう」と考え、すぐに手を動かしてしまうことが多くありました。
しかしその結果、途中で何度も行き詰まり、「そもそもこの機能は何のためにあるのか」「この値はどこから来るのか」といった基本的な部分で迷ってしまい、作業をやり直すこともしばしばありました。
そうした経験から、「タスクを理解できる単位まで分解すること」が、進捗を生む第一歩だと感じるようになりました。
細かく切り分けて考えることで、理解できている範囲と曖昧な部分を可視化でき、課題を明確に整理できます。
また、分解の過程で「このデータ、本当にこのAPIから取得できるのか?」「この順序で処理して問題ないのか?」といった着手前の段階で矛盾や不明点に気づけることも増えました。
実際、タスクを小さく整理していく中で仕様の抜け漏れを発見し、事前にチーム内で確認できたことで、後から大きな修正を防げたこともあります。
今では、いきなり手を動かす前に、「このタスクは何を目的としているのか」「自分がどこまで理解できているのか」を一度立ち止まって整理するようにしています。
時間はかかるように見えても、そうすることで結果的にスムーズに進められることが多くなりました。
わからないことをわからないと言う勇気
新卒の私にとって、任された仕事を最後までやり遂げることは大きな達成感があります。
しかし同時に、「任せてもらっている以上、自分で何とかしなければ」という責任感から、つい一人で抱え込んでしまうこともありました。
簡単な疑問についてはすぐに質問できていたのですが、仕様の複雑な部分や技術的に難しい内容では、理解が追いつかないまま実装に入ってしまい、結果として作業に時間がかかり、進捗が思うように出ないこともありました。
印象的な経験として、仕様が複雑かつ技術的にも難しい機能を任されたときのことをお話しします。
担当していた先輩が休みだったため、PMの方から詳しい説明を受け、ある程度理解できたつもりで実装に入りました。
しかし、実際に手を動かしてみると、自分が思っていたよりも複雑で頭が混乱してしまいました。その結果、理解が中途半端なまま進めてしまい、作業に時間がかかって進捗も滞ってしまいました。
この経験から、次のことを強く意識するようになりました。
一度聞いて理解できなかった内容は、たとえ時間がかかっても自分が理解できるまで質問すべきだということです。
先輩の時間を取ってしまうのではと遠慮してしまうこともありますが、中途半端な理解のまま仕事を進めてしまうと、結果的に進捗を遅らせ、チーム全体に影響を及ぼしてしまいます。
理解できるまで質問する勇気は、決して弱さではなく、責任感の表れです。
それは自分の成長だけでなく、チームの成果を守るための大切な行動だと今では感じています。
自分の進捗や疑問を正しく伝えるコミュニケーション
私が参加したプロジェクトでは、毎日「昼会」があり、PMの方も交えて質問や進捗共有を行う時間が設けられていました。
私も疑問点については、昼会で全体に共有できるよう心がけていました。この心がけは良かったのですが、その中で、疑問点や進捗を正しく伝えるコミュニケーションの重要性を強く感じました。

設計フェーズでは、仕様の矛盾や疑問点が多く出てくることがありました。
自分が気づいた疑問点や矛盾点を正確に伝えることは意外と難しく、伝え方ひとつでチームへの影響も変わることを実感しました。
そのため、まず自分自身がしっかり理解した上で、正しい言葉で伝える、どの資料をもとに考えたのかを整理して、会議の時に時間を効率的に使えるように準備することが大切だと感じました。
今では、思いつきで質問するのではなく、疑問点を聞く前にどの資料を見て、何を疑問に思っているのか、すぐにわかるような伝え方と資料をすぐに展開できる状況を揃えてから質問や共有を行うよう心がけています。
進捗の報告についても同じことが言えます。
他のメンバーには自分の状況は見えないため、「どこで詰まっているのか」、「作業の進捗を何割程度進んでいるか」といった形でわかりやすく伝えることが必要です。
場合によっては、先輩からフォローしてもらえることもあるため、無理に良く見せようとせず、素直に「ここで詰まっているのでフォローをお願いします」と伝えることで、結果的にチームでの開発をスムーズにすることにつながると感じました。
「共有がない=周りから見たら止まっているのと同じ」という考え方のもと、報告・相談・共有を意識することは、チーム開発において新卒エンジニアが身につけるべき大切な姿勢だと感じています。
まとめ
入社半年間のプロジェクト経験を通して、私は技術力の向上だけでなく、チームで成果を出すために大切な姿勢を学びました。
新卒のうちは知識や経験が不足して戸惑うことも多いですが、これらの意識を少しずつ積み重ねることで、自分自身もチームも着実に前に進めると感じました。
新卒だからと変に気負うことなく、積極的にチームに貢献できるよう行動していきたいと思います。
入社して初めてのプロジェクトだからこそ得られる気づきや学びは多く、こうした経験を活かして、今後もエンジニアとして成長を続けていきたいです。